はじめに

こんにちは、透華ママ〈とうかママ〉です♪
「家計簿をつけようと思っても、気づけば挫折している」
「そもそも何のためにつけるのかわからない」
そんな経験はありませんか?
実は、家計管理は完璧にやることよりも“続けること”が大事。
この記事では、家計簿をつける意味やメリット、挫折の理由、そしてズボラでも続けられる工夫をご紹介します。
家計簿をつける理由とメリット
家計簿をつける目的は、お金の流れを「見える化」することです。これにより、無駄な出費に気づけたり、将来の貯蓄計画を立てやすくなります。
主なメリット3選
- お金の不安が減る:「今月大丈夫かな?」という漠然とした不安がなくなる
- 節約意識が高まる:記録することで無駄遣いを意識できる
- 目標に近づける:教育費や旅行など、目的に沿った貯蓄が可能になる
家計簿を挫折してしまう人は多い
調査では、家計簿をつけたことがある人は7〜8割。しかし、そのうち半数以上が挫折しています。
挫折の理由は?
- 毎日の記録が面倒
- 数字が合わずストレスになる
- レシートがたまって処理できない
- 効果を感じられず続かない
👉 大切なのは「細かく完璧にやる」ことではなく、続けられる仕組みを作ることです。
ずぼら家計管理を続ける7つのコツ
完璧じゃなくてOKと割り切る
1円単位で合わなくても「食費が多かったな」と把握できればひとまずは十分。4~5つの項目に分けてざっくりと支出を把握することが第一歩!
月1回だけ振り返る
- 毎日は不要
- 給料日や月末に30分だけまとめてチェック
これだけでも「使いすぎ項目」が見えてきます。
完璧にやらなくてもいいと決める
- 記録を忘れた日があってもOK
- まとめて書いてもOK
最初から「ゆるくやる」と決めることで挫折しにくくなります。
固定費は年1回見直す
毎月の努力より、一度の見直しが効果大。
- スマホプラン
- 保険
- サブスク
そのまま考えずに契約していませんか?スマホプランも変化がありますし、年に1回「固定費点検日」を設けてみましょう。
項目は4〜5個に絞る
細かい項目分けは不要。以下くらいが続けやすいです。
- 食費
- 光熱費
- 固定費(家賃・保険・通信費など)
- 日用品
- その他
ご自分の家計に合った項目をピックアップして確認していきましょう。
家計簿はアプリでも手書きでも好きな方で
使うツールは性格に合わせて決めていきましょう!
- アプリ派:自動化でラクに管理したい人
- 手書き派:書くことで意識を高めたい人
におすすめです。まずはアプリでもノートでも、自分に合う方を選べばOK。正解はないので、いろいろ試しながら探してみてください。
家計簿帳は100均でも十分
今は色んな家計簿が売られているので、自分に合うものが必ずあるはずです。
ただ、自分に合う家計簿を買っては試すってことは難しいですよね。自分が決めているものがあれば、それを使っていただければいいのですが、初めからわざわざ高価な専用帳を買う必要はないと思います。
最初は100均で購入できるスケジュール帳を試すのもおすすめ!支出を「気軽に書ける場所」を作り出せればよいでしょう。
楽しく続ける工夫
家計管理を「義務」にせず、楽しさを加えると習慣化しやすくなります。
例えば…
- ノーマネーデーにシールを貼る:お金を使わなかった日を可視化して達成感アップ
- ご褒美ルールを設定:記録を1か月続けられたら・ノーマネーデーが先月より増えたらカフェやスイーツでプチ贅沢等自分を甘やかしちゃおう!
- 小さな成功を喜ぶ:「先月より光熱費が1,000円減った」など数字で成果を実感
まとめ
家計簿を続ける秘訣は、正確さではなく習慣化にあります。
- 完璧を求めずざっくり管理
- 月1回の振り返りで十分
- 支出はシンプルに4〜5項目
- アプリでも手書きでも、自分に合う方法でOK
- 100均ノートで気軽にスタート
- ノーマネーデーやご褒美ルールで楽しく続ける
家計管理を「義務」ではなく「生活の一部」として取り入れることで、自然とお金の流れが見えるようになります。小さな工夫を積み重ねれば、いつの間にか「気づいたら続いていた」「お金がちゃんと貯まっていた」という状態に近づけます。
そして大事なのは、今日からほんの少し行動すること。
例えば「100均のスケジュール帳に食費だけ書いてみる」「アプリに口座を1つ登録してみる」など、どんなに小さな一歩でも大丈夫。
👉 まずは今日から“1行だけ”書いてみるところから始めてみませんか?
その一歩が、未来のお金の安心につながります。
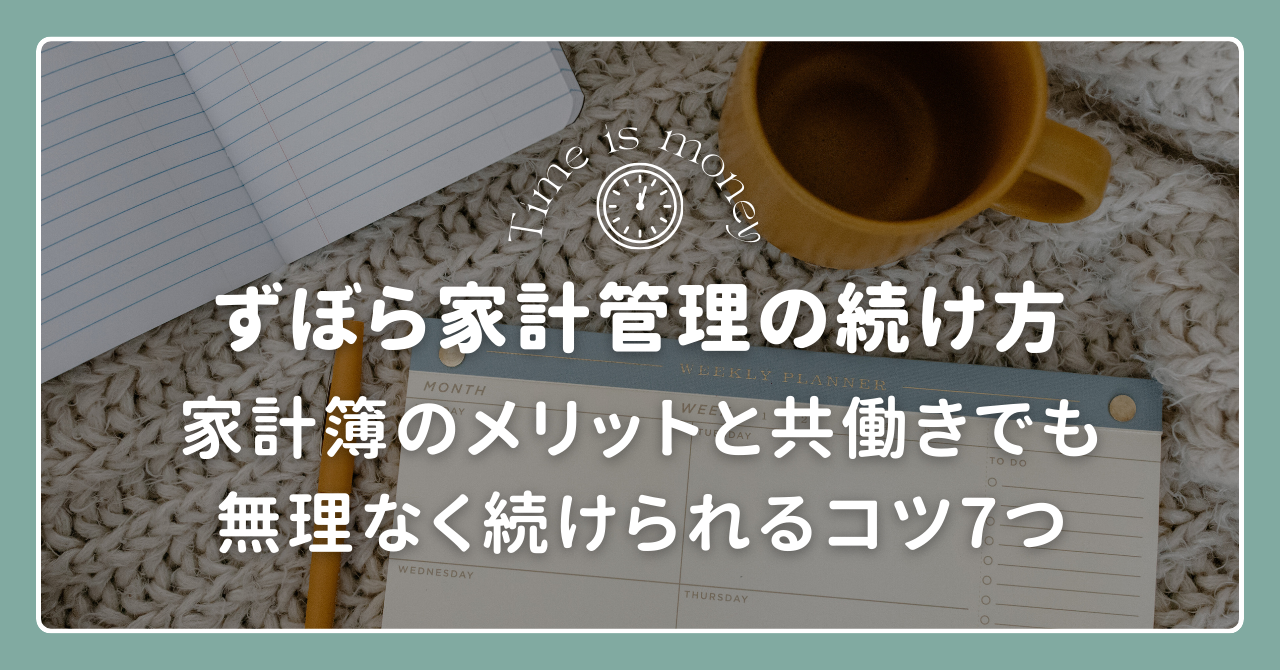
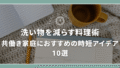
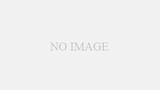
コメント